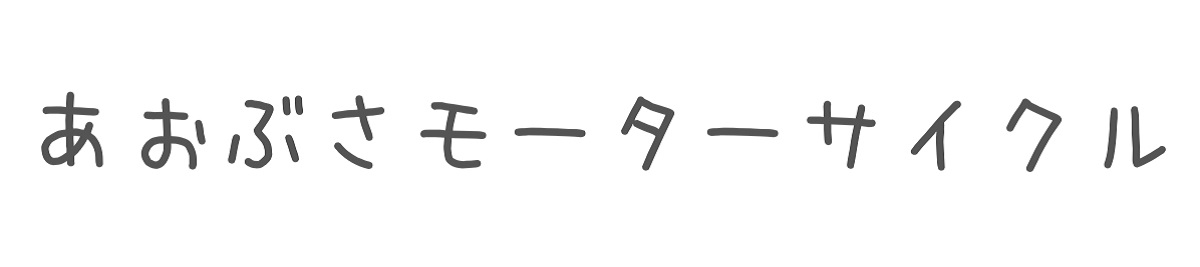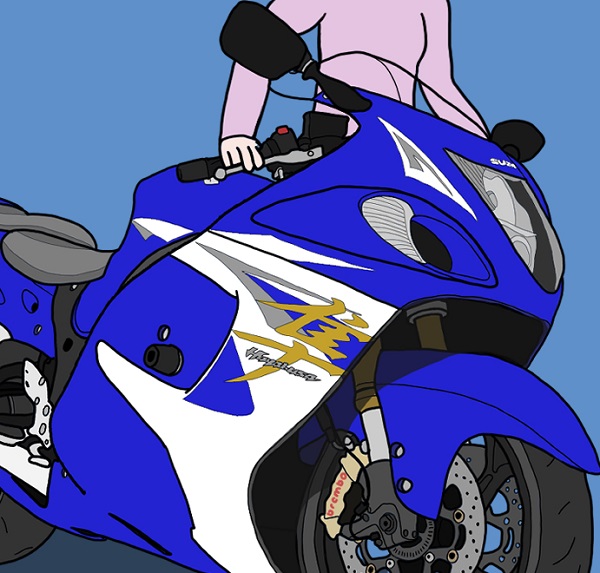Sponsored Link
排気量250ccを超えるバイクには車検があります。
車検の時期になると、中型・大型バイクのユーザーはバイク屋さんにバイクを預けるわけですが、中には「少しでも車検の費用を安くしたい」という理由からユーザー車検を選択する人もいます。
※車検には、バイク屋さんに代わりに通してもらう「代行車検」と、自分で通す「ユーザー車検」の二種類があります。

とは言ったものの、ユーザー車検なんてやったことがないし、そもそもどうやって通せばいいのか分からない・・という人も少なからずいるかもしれませんね。
そこで今回は、バイクのユーザー車検の手順をまとめました。
「少しでも車検の費用を安くしたい」「ユーザー車検の手順が分からない」「自分で車検を通してみたい」という人の参考になれば幸いです。ぜひご一読を。
Sponsored Link
もくじ
バイクを点検整備する
当たり前の話かもしれませんが、バイクが「車検に通る状態」でないと車検に通りません。
手順が云々とか言う前に、まずはバイクを点検し、不具合箇所がないか確認しましょう。
点検する「だけ」ではダメですよ?不具合箇所があったらちゃんと直してください。
もし不具合箇所があった場合は、自分で直せるところは自分で直し、自分で直せないようならバイク屋さんに持ち込んで直してもらってくださいね。
※レース用のサイレンサーを付けていたら検査で引っ掛かります。車検を受ける前に、純正品または政府認証品のサイレンサーに交換しておきましょう。


Sponsored Link
必要な書類を揃える
点検整備は終わりましたね?
次は、車検に必要な書類を揃えます。
車検に必要な書類は以下の通りです。
・自動車検査証
・自動車損害賠償責任保険証明書(新、旧の2枚)
・納税証明書
・定期点検整備記録簿
・印鑑(ただし、車検を受けるのが本人の場合は不要)

定期点検整備記録簿の入手方法
定期点検整備記録簿とは、簡単に言うと「点検整備(法定点検)の結果を記録するもの」です。
定期点検整備記録簿を入手する方法は
・バイク屋さんで貰う
・バイクのメンテナンスノートに付属しているものを使う
・ネット上にあるもの(PDF)を印刷する
といったものがあるので、お好みの方法で入手してください。

定期点検整備記録簿は入手できましたね?
次に、先ほど点検整備したバイクの状況を思い出しながら定期点検整備記録簿を記入していきます。
何やら難しそうなことが書いてあるように見えますが、よーく見てみると分かることばかりなので、一つづつ空欄を埋めていきましょう。
また、中には「分からない」または「そもそも確認することができない」項目があるかもしれませんが、そこは空欄のままでも構いませんし、それで指摘されることもありません。
ただし、あまりにも空欄が多いと「ホントに点検整備したのかな?」と思われるかもしれませんので、分からないことがあったら可能なかぎり自分で調べ、なるべく空欄を少なくしておきましょう。

Sponsored Link
検査の予約をする
次に、検査の予約をします。
国土交通省のホームページにアクセスし、検査の手続きをしましょう(※検査の種類は「継続検査」です)。
なお、予約が完了したら「予約番号」が表示されますので、その番号を書き留めておきましょう。当日、その番号が必要ですから。

ネットで予約したくない(できない)場合は
実を言うと、ネットを使わなくても予約する方法があります。
今の時代、陸運支局に自動車検査証(以下、車検証)を持って行けば検査の予約をすることができるようになっています。

窓口に置いてあるパソコンに必要事項(例:氏名、電話番号)を入力し、車検証の右下にあるQRコードを読み込めば検査の予約ができます。
平日に陸運支局に行くことができるのであれば、窓口で検査の予約をするという手もありますので、ネットで予約するのが面倒くさい、あるいはネットで予約すること自体ができないのであれば直接陸運支局に行きましょう(※陸運支局に行く前に、受付時間を確認しておきましょう)。


テスター屋さんで光軸合わせをする
これでようやく車検に臨める・・わけではなく、その前にすることがあります。
ヘッドライトの光軸(光が照らす方向)合わせです。
ヘッドライトの光軸がずれていると検査で引っ掛かりますので、車検を受ける前にテスター屋さんで光軸合わせをしてもらう必要があります。
なお、テスター屋さんは「陸運局の近く」にあることが多いです。もしテスター屋さんがどこにあるか分からなかったら、バイク屋さんに聞いてみましょう。
※数千キロ走っているなら十中八九ずれています。検査で引っ掛かるとまた再検査を受けることになっちゃうので、面倒くさがらずに光軸合わせをしておきましょう。

ちなみに光軸合わせといっても、特別なことは何もする必要はありません。
バイクに乗ってテスター屋さんに行けば、テスター屋さんの方から「ヘッドライトの光軸合わせですか?」と聞いてくれますので、テスター屋さんの指示通りにバイクを動かしましょう(後はテスター屋さんが光軸を合わせてくれます)。
※光軸合わせの料金は1,600円前後です。ただし、ヘッドライトの電球が切れていたら電球代も加算されますのでご注意を。

Sponsored Link
窓口で印紙・証紙を購入する
車検当日(検査の予約をした時間よりも早めに)に印紙コーナーの窓口に行き、「自動車重量税印紙」「自動車審査証紙」「自動車検査登録印紙」を購入します。
これらの印紙・証紙は、後で書類に貼り付けて提出しますので紛失しないよう注意してください。
なお、印紙・証紙の合計は5,500円(※2022年5月時点)です。あらかじめ用意しておきましょう。

書類に記入する
次に、検査を受ける前に書類に記入します。
窓口に置いてあるディスプレイの必要書類(自動車検査証、OCR申請書、自動車重量税納付書)にタッチし、車検証の右下にあるQRコードを読み取れば、プリンターから書類が出てきますので、それらの書類の必要事項を記入します。
窓口の周辺に「書類の記入例」が提示されていますので、記入例を見ながら一つづつ記入しましょう。
※なお、書類は指定の時間(自動受付の時間帯)にならないと印刷できませんので、事前に確認しておくことをおすすめします。







書類の必要事項に記入したら、印紙コーナーの窓口で購入した印紙・証紙を書類に貼り付けます。これも記入例に貼付箇所が書いてありますので、それらを参考にしながら貼り付けましょう。


Sponsored Link
検査場で検査を受ける
予約した時間になったら、検査場に行きます。
一番乗りでなければ、あなた以外のクルマやバイクも並んでいると思いますので、そこで並んで待ちます。

なお、ここでも書類の提示が求められます。書類はクリアファイルなどに入れておき、書類をすぐに出せるようにしておきましょう。

また、ヘルメットはリアシートの上にでも固定しておきましょう。
検査場にヘルメット置き場はありませんし、ヘルメットを被った状態だと検査員の指示がよく聞こえません。
検査でモタついていると「(検査に)慣れてないんだったらヘルメット外してください」って言われてしまいます。ご注意を。

検査場では、検査員の指示に従いながら検査を進めていきます(※自信がないのであれば、検査員に「ユーザー車検はじめてです」と伝えてください)。
ここで何も引っ掛からなければ検査は終了です。そのまま検査場内の総合判定ボックスに行って書類を提出し、問題がなければ合格となります。
※もし不合格だった場合は再検査となります。その日のうちに不具合箇所を直し、16時までにもう一度検査を受けてください。
総合判定ボックスで合格の判定が出たら、持込検査の窓口に行って書類を提出します。
しばらくすると、新しい車検証とステッカー(自賠責)がもらえます。
新しい車検証をもらったら、間違いがないか確認しましょう。
ごくまれにではありますが、備考欄の値(走行距離計表示など)が間違っていることがあります。
もし間違いがあったとしても、当日中なら修正することができますので、車検証をもらったら忘れず確認しておきましょう(もし間違いがあったら、即座に窓口の方に申し出てください)。

車検証に間違いがなかった、あるいは間違いを修正してもらったら、ナンバープレートのステッカーを新しいものと貼り換えます。
これにてユーザー車検は終了です。おつかれさまでした。


Sponsored Link
最後に
以上、バイクのユーザー車検の手順でした。
一見面倒くさそうに見えますが、実際にやってみるとそこまで難しくありません。
それこそ二回目以降になると、何も(つまり、この記事も)見なくても終わらせることができるようになります。

ただし、それは「検査で引っ掛からなかったら」の話です。そうならないためにも、日ごろからバイクを点検整備しておく必要があるわけですね。
検査で引っ掛かって、不具合箇所を直してまた再検査・・・なんてことになったら、余計な時間と労力が掛かってしまいますから。
※余談ですが、検査で引っ掛かると自動車検査票に「再検」というハンコが押されます。

ユーザー車検は代行車検よりはお金は掛かりません。
なぜ代行車検が高価に思えるのかというと、法定費用の他に代行手数料や工賃(または部品代)が上乗せされているからです。
ですが、ユーザー車検なら代行手数料が掛かりませんし、日ごろから点検整備している人だったら直す箇所も少なくて済みます。
そういう理由から「なるべく車検費用を安くしたい」というのであれば、ユーザー車検の手順を覚えることをおすすめします。もちろん、日ごろから点検整備することが大前提ではありますが。

申し添えておきますと、点検整備費用ってのは「法定点検」のことです。
「車検」の有無にかかわらず、バイクで公道を走るのであれば必ず点検整備をしなければいけません。
なので「ユーザー車検だったら法定費用だけでいいんじゃないの?」って思っていても、結局、点検整備費用(部品代、場合によっては工賃)が必要になるわけです。
「250は車検がないから維持費が安い!」「車検があるバイクは維持費が高い!」みたいなことを言う人は今でもいますが、実際は重量税と印紙代(それと、あえて言うなら、陸運支局に行く手間)程度の差しかありませんので、けっして丸呑みにしないでくださいね。



それでは、この辺で。
あなたが、車検の有無に限らず、どんなバイクに乗っていようと、ずーっと安全にバイク生活を満喫できますように。

普段からメンテナンスをしとれば消耗品の消耗だけで済む。そいつを怠るから、壊れなくてイイところが壊れるのだ。
ブレーキに限らず、全てのパーツは必ずや衰える。そしてそれは徐々にやってくる。だから、乗っていても気付きにくい。
その頃になると、ライダーはバイクに慣れきっている。すると、「このバイクはココがイマイチ」などと言い出して安易にカスタム・・・ってパターンは意外と多い。
パーツ本来の力を知らずして、カスタムはあり得ない。
まずは本来の性能を維持。カスタムはその先にある。
メンテナンスこそ、カスタムの第一歩なのだ。ラララ~♪
(カスタム虎の穴 vol.3【ブレーキ編】 31ページより)
Sponsored Link